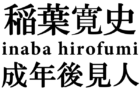おひとり様の終活に強い行政書士、社会福祉士
主な業務内容

稲葉寛史行政書士
皆様、初めまして。 行政書士の稲葉寛史と申します。
私は介護医療の現場で13年間、ケアマネジャー、精神科クリニックの相談員として働いておりました。
その経験の中で、最期の看取りをさせて頂いた機会が何度もありました。
ご利用者様やご家族様の意向を伺い、延命については末梢点滴やIVH、心臓マッサージの施行、AEDの使用、人工呼吸器の挿管等、御本人様の尊厳を守った上で、自然に看取り、看取られることが出来るように、介護士や看護師、主治医、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、ケアマネジャーがチーム一体となり、サービスの提供をしてまいりました。
そして、多くのご家族様からは、素晴らしい最期を迎えられて良かったと感謝して頂き、支援者として最後まで寄り添う良いサービスが出来たと感じておりました。
しかし、私達の介護の仕事が終わった後、ご家族様は、葬儀のことや市役所に届け出る手続き、そして、相続のことで悩まれるケースが大変多くありました。
例えば、「死後の手続きは何が必要になるんでしたっけ?」とか、「相続やってくれる人知らない?」、「遺産分割で揉めてるんだけど、親の介護を受けていた時の記録を教えてくれない」と言った問い合わせがありました。
私はその都度、どうしてあんなにいい最期を迎えることが出来たのに、その後落ち着かないんだろう。 どうして、ケアマネジャーとしての立場はご家族様から色々聞かれるが、私は答えることが出来ないのだろうか。 と自分自身を不甲斐ないと感じる事が多々ありました。 その為、私自身が法律という知識を身に付け、介護から最期までだけでなく、成年後見、そしてその後に続く、死後事務や相続の支援を行い、シームレスなサービスの提供が出来れば、御本人様もご家族様も不安や戸惑いなく、最期を迎えられるのでは無いかと感じておりました。
弊所では、身上保護に真心を入れた成年後見のサービスを提供し、介護〜終末期、死後、相続でご不安な方のご支援に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。
ご相談事例

成年後見人は、被後見人の利益を最優先に考え、個々の状況に応じた適切な支援を提供することが求められます。そのため、法的知識や倫理観を持ち合わせた専門家の選択が重要であり、様々なご相談を受けることがございます。
お問い合わせ
介護予防支援業務、相続関連業務、入管業務、その他許可申請のご相談は、稲葉寛史 行政書士事務所へお気軽にご相談ください。 その際は、必ずご連絡先・ご担当者名をお知らせいただけますようお願いいたします。